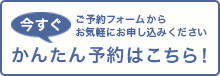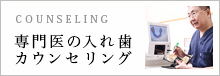院長のブログ
江戸の入れ歯師たち
江戸の入れ歯師たちこの本は長谷川正康先生がかかれた本ですが日本の木床義歯のお話ですが西洋は
歯がある場合今のブリッジみたいに針金や金属バンドで結紮したり板バネで維持したので見栄えだけで
素試薬機能はありません。
しかし日本は柘植を少しずつ削り合わせていきました。
もちろん咬合理論や顎運動理論はありませんので平面吸着だけですが辺縁の封鎖はできませんから咀嚼
はおかゆかもしれません。しかし前歯の部分は人工歯の形態ですが咀嚼の咬合理論が確立されていないので
臼歯部はフラットにして鋲を打ち付けていますね。多分に咬合高径も低くつくりいつも苦虫噛むような
顔と想像されますね。適正な咬合高径は今の歯科医学でもなかなか難しいのです。決定法がいろいろあり
見た目や、発音、筋電図、最近接発音、など最低2とうり以上で決めますね。
温故知新、歴史を調べると日本はすごい国ですよ!400年前織田信長の時代に欧米ではできない
大気圧の原理で吸着して機能する入れ歯が存在したのですから。
現在では総入れ歯の理論は咬合論、顎運動そして嚥下、発音などを機能解剖学的に診断して治療義歯にて
舌の運動、頬粘膜の封鎖を3次元的にインプットして作ります。これはAIにはできません。
アナログ的な匠の技です。江戸時代と変わらないのかな?しかし100年前ギージ先生が
考えた理論からパウンド先生、ウーリッヒ先生、ゲルバ―先生の理論を加味した遠藤のパイロットデンチャー
システムは最善の方法と50年の臨床歴からきっぱりと言えます。昨日も30年前の総入れ歯の92歳になられる患者さんが定期検診に来院されましたが人工歯も陶歯コンヂロフォーム、ゲルバ先生の理論です。
バイトアイCランクなのでAランクアップして、AHラインの封鎖のみで済みました。
この方はこれから食べる楽しみを享受したいので定年の退職金でまず総入れ歯をと作られたのですが
それから30年役に立ち患者さんともども私もうれしく思いました。
まだまだ5年10年と使えればと思います。

2025/03/23